100年間の海の不思議が判明
Table of Contents
ピピ島+シャークポイント3ダイブ
証です。初日はラチャ方面で潜ったK様の、2日目にピピ島でダイビングされたご様子を投稿します。さて、「100年間の海の不思議が判明」とは何でしょうか?

昨晩はしっかり眠れたおかげで、旅の移動と初日のダイビングツアーの疲れもなく元気にピピ島へレッツゴーです。
雨季の風も微量、潮流も軽くナイスコンディションです。
ダイブプロフィール
■ダイブ1/ピピ諸島ビダノック島/Time in 11:01-Time out 11:46/最大深度20.9m
■ダイブ2/ピピ諸島ピピレー島タートルロック/Time in 12:58-Time out 13:43/最大深度18.7m
■ダイブ3/シャークポイント/Time in 15:00-Time out 15:46/最大深度19.0m
■水温29℃
■透視度15M

ピピ島では透視度、透明度ともにすっきりしませんでしたが、大量の「キンセンフエダイ」や「ヨスジフエダイ」の群れと一緒に泳ぎました。
残念ながらブラックチップシャークはお目に掛かれませんでしたが、アンダマン海固有種「レッドサドルバックアネモネフィッシュ」のコロニーをじっくり観察することができました。
100年間、分からなかった謎
「レッドサドルバックアネモネフィッシュ」はニモが代表されるダイバーに人気のクマノミの仲間です。彼らはイソギンチャクの中でコロニーを形成しながら一生を過ごします。
そして、クマノミは毒を持つイソギンチャクに隠れながら外敵から身を隠しているわけですが、なぜクマノミだけが毒が平気なのかはこの100年間、ちゃんとした原因が分かっておりませんでした。
そもそもイソギンチャクの毒は
・外敵から身を守るため
・刺胞と呼ばれる触手にある細胞から神経毒が発射される
・神経毒だからその場で麻痺する
その毒性が強いから普通の魚はイソギンチャクに近づけないでいるわけです。
そして、毒の影響が無いクマノミはその触手の中で暮らしいます。
・外敵から身を守る
・毒に強いイソギンチャクを食べる魚から追い払う。
・イソギンチャクが食べる小魚、エビ動物プランクトンを与える
(触手で中央の口に持っていく手助け)
・たくさん動き海水を循環させることで新鮮な環境にする
と、単なる「捕食者から身を守る」だけにとどまらず、イソギンチャクとクマノミは共生しているのです。では、なぜクマノミはイソギンチャクの毒の影響が無いのでしょうか?それはこの100年間にわたり、明確に判明していませんでした。
100年間の海の不思議が判明
それには、様々な説がありました。
①自分として認識説
イソギンチャクとクマノミの身体に付いている粘液が似ているから、イソギンチャクが自分の身体と認識している
②粘液分厚い説
皮膚を覆う粘液が分厚くて毒が届かない
③トリガー回避説
クマノミの粘液に毒を発射させる分子が無い。つまりトリガー(引き金)させない

2025年2月にそれが判明したのです。(沖縄科学技術大学院大学(OIST)の研究グループが発見)
答えは、、、、、
イソギンチャクは、多くの生物の表面にあるシアル酸(糖分子)に反応して毒を発射します。
クマノミの粘液にはそのシアル酸分子(糖分子)が成長に伴って減少していくのです。
クマノミにはイソギンチャクが毒を発射するトリガーが少ない。発射させない!!
ただぼ~と見るだけじゃなくて、少しぐらいの情報があるとより楽しくなりますね。固有種好きなK様にぴったりのお話でした。
が正解でした!!(ちなみにイソギンチャク自身もシアル酸(糖分子)を持ってないので、自分自身を刺さないで済みます。ついでに判明した模様です)
さらには、コロニーで一番大きいのがメス、そのメスが死んだら次に大きいのがメスに転換する。
などなど、色んな情報を聞いた上でK様と一緒に発見した「レッドサドルバックアネモネフィッシュ」をじっくり観察しました。
大きなバラクーダ
ピピ島でたっぷり遊んだ後、最後にシャークポイントです。
あいにくサメには会えませんでしたが、とっても大きなバラクーダ「ピックハンドルバラクーダ」が優雅に泳ぐ姿を捉えることができました。
K様も初めて見たので喜びです。

2日目のダイビングも無事終了。
明日はいよいよ最終日です。夜ごはんは美味しいイタリアン行きましょう。大きなお魚見るとすぐにお腹が減ってきます。
そして、クマノミ談議にでも華を咲かせましょう!!
今日もありがとうございました。



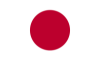

コメントを残す